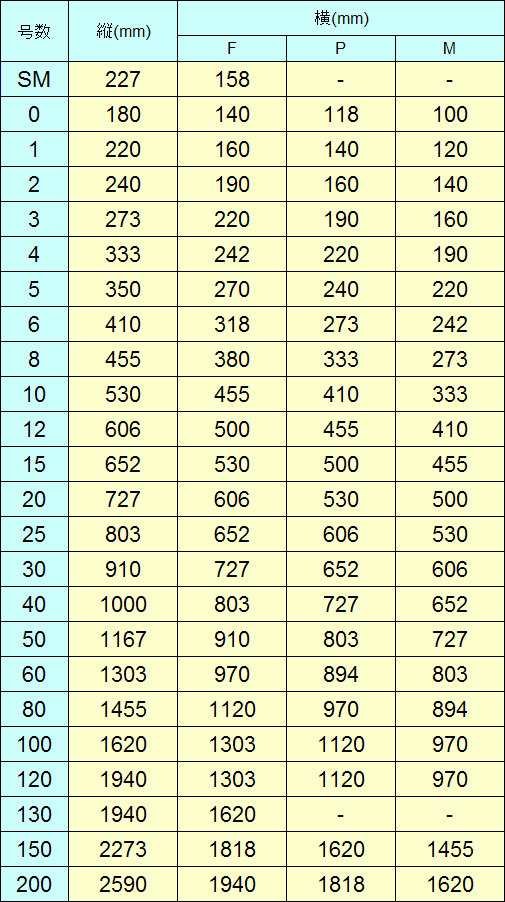「キャンバスを角から張る (2)」の問題点は完全解決をみておりませんが、「キャンバスを角から張る (3)」の問題はどうにか解決できた様です。
木枠側面にプッシュピンを刺し、木枠裏面でステープル留めする際には”ゆるみ”が発生してしまう問題がありました。
この問題を解消する方法として編み出したのが下記の手法。 木枠側面、裏面近くの縁ギリギリにプッシュピンを刺してキャンバスを張った後、同じ木枠側面にステープルを打ち込みます。
木枠側面、裏面近くの縁ギリギリにプッシュピンを刺してキャンバスを張った後、同じ木枠側面にステープルを打ち込みます。
上図手前がキャンバス表面側になるんですが、この様にするとテンションのかかったプッシュピンの手前にステープルを打つ事になるので「ゆるみ」は発生しません。
プッシュピンの間隔はステープラーが入る隙間を考えつつ、適当にやりましょう。
プッシュピンをあまりギリギリに刺しすぎると… 木枠裏面に突き出てしまったり。注意。
木枠裏面に突き出てしまったり。注意。
プッシュピンを抜いた後はこうなります。
“本式”ではキャンバスをプッシュピンで留めた後、1日置いてゆるみが発生しないか確認してから適宜張り直しの作業を経て、ステープルで固定するというやり方ですが、その手間が有効なのかどうかよくわからんので私は即日ステープルで固定します。
プッシュピンでの仮止めというのは抜き差ししやすく、張り直し作業には非常に有効なのですが、キャンバス張りの作業中にそんなに張り直しが必要になる事もありません。
だったらプッシュピンなど使わずにいきなりステープルで固定していった方が良いんじゃないかって気もします。
今回の手法も多少こなれてきたので、次回からはいきなりステープル固定法でやってみるとします。
木枠についての考察
キャンバス木枠について今までいくつか述べてきておりますが、新事実が発覚したのでお知らせしておきます。
今までよく異なる号数の縦枠・横枠を組み合わせて変形のキャンバスとし、制作してきました。
同じホゾが切ってあるので異なる号の縦横は組み合わせる事が出来る…というのはどこぞのHPやら雑誌やらでも紹介されていたと思いますが、マルオカに問い合わせたところ以下のような回答。
そのような使用法はハナから想定しておらず、F10号ならF10号の縦枠・横枠・中桟と一組で製造しており、ノコ歯の厚みやら何やらで微妙にホゾのサイズに誤差が生じるので異なる号数の枠とは完全な互換性はない。
あんぐり。
220mmの横枠はまとめて加工したものをF3号、P4号、M5号…と分けているのではなく、同じ220mmでもF3号用の横枠、P4号用の横枠、M5号用の横枠…と個別に加工しているという事。
もうこうなると数値の互換性って一体何…
まあ実際のところは組めない事はないのですが(実証済み)、たまにユルユルだったりキツキツだったりするのはそういうワケか。(木材の乾燥具合などにより生ずる変形かと思ってたが)
第86回白日会展
こっそりと出品しておりましたが、どうやら入選できた様です。 ▲ひさびさのデカ画像(クリックで拡大)
▲ひさびさのデカ画像(クリックで拡大)
かかった費用がムダにならずに一安心。
しかし地方からの出品には金がかかりますなあ。
業者に搬入代行お願いすると往復で2万以上。
入選を果たせなかった場合、出品料1万と併せて3万円をドブに捨てる事に。
駆け出しの若手、しかもこのご時世にはリスクが高すぎますよ。
(事実私も借金して出してる)
地方からの若手開拓という面でみると、大きなネックになっていると思われます。
有望な人材がいても、ある程度余裕のあるやつじゃなきゃ世の中にゃ出れないって事ですかな。
作品は1455×894mmの大作で、実は以前チラリと記事にした天然ウルトラマリンを使った作品です。
ラピスラズリと、紫陽花のグレーズにも多少使ってます。
ラピスラズリの部分はあからさまにマチエールが現れているので気づく人もいるかも知れませんが、紫陽花もよーーく見ると、大きめの顔料が粒として確認できるはずです。
これはムラに見えるので余り良い使い方とは言えませんでした。
とろこで規定によると会期後1年間は白日会に著作権を「帰属する」との事。
このあたりのところは十分チェックしておらず不意を突かれました。
(規定文の通りなら1年間は私が勝手に作品の画像等を使えない事になり、個展の図録やら何やらの際いちいち使用許諾を貰わねばならなくなる。)
近いうちに事務局に連絡していろいろ訊ねなければなりません。
白日会展詳細はコチラで
「号」についての考察
諸外国の事情は知りませんが、日本に於いて油彩作品の価格は概ね「号数」によって決められる様です。
作家毎に設定された「評価額」というものがあり、それはつまり1号あたりの販売価格で、仮に「号5万」という評価額の作家が10号の作品を描いたならば、50万円で販売されるという事になります。
号数が販売価格の算出に直結し、また作家が頂く画料も号数で決まるという事です。
では「号」とは一体何なんでしょうか。
一般的には大きさの基準と考えられている様ですが、実は「基準」となり得るシロモノではありません。
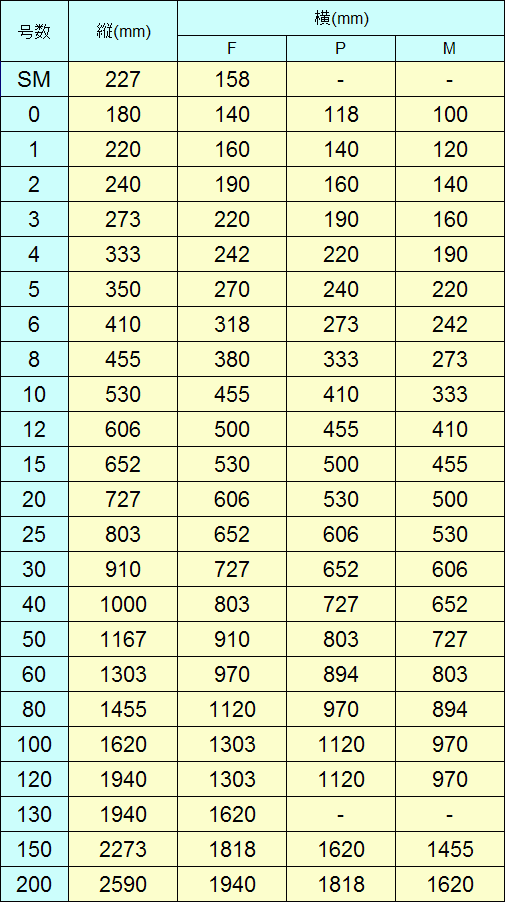 数値はマルオカHPを参考。
数値はマルオカHPを参考。(5号や130号はマルオカ独自規格でしょうか。画材屋で見たことありません。)
注目は次の表から。
▼左:号数毎の面積 右:各号Fの面積を1とした場合のS,P,Mとの面積比
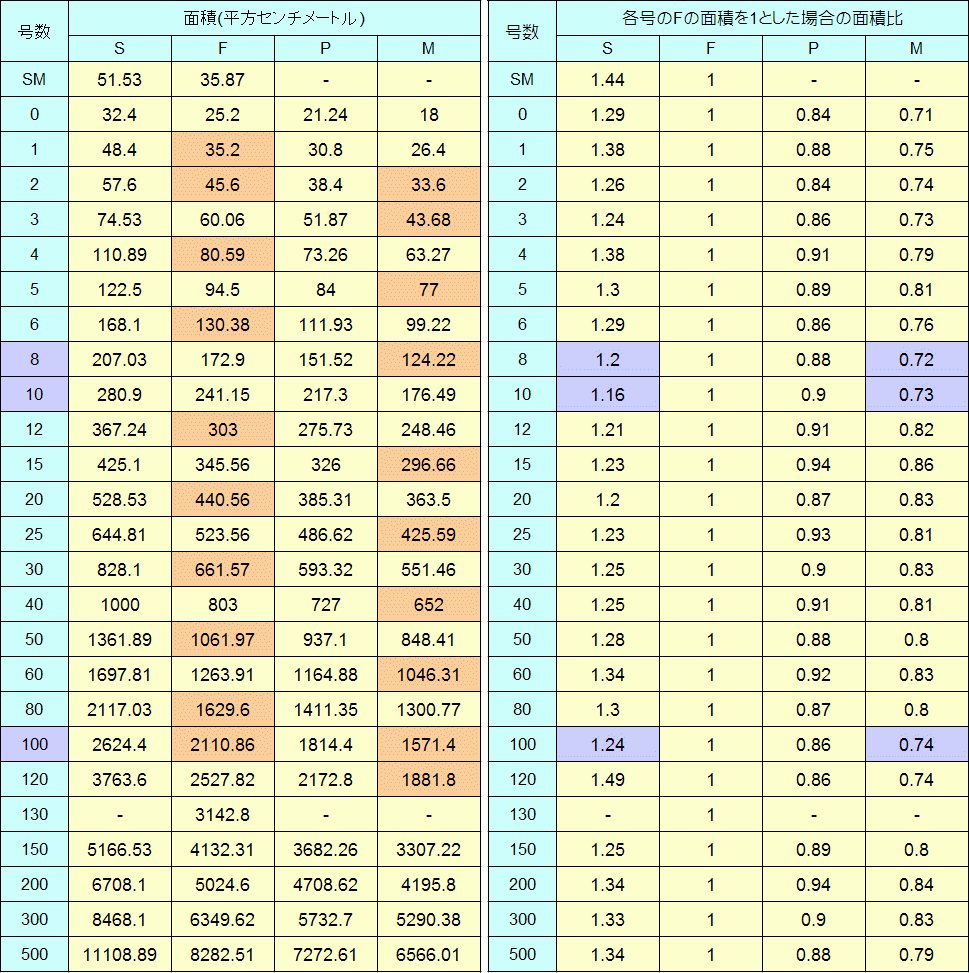 通常、作品の価格、画料については各号F、P、Mとも変わりなく、なぜかSについてのみ「面積が広いから」との認識からか、若干高めに設定されます。
通常、作品の価格、画料については各号F、P、Mとも変わりなく、なぜかSについてのみ「面積が広いから」との認識からか、若干高めに設定されます。各号の面積を比べてみると、疑問に思いませんか。
右表の紫色で示した8、10、100号に至っては、FとSの比率よりFとMとの比率の方が開きがあるのですが、これらに限ってMは安くするという話は聞いたことがありません。
また左表オレンジ色で示したものは、号数で面積が逆転するものです。
つまりM2号よりもF1号の方が広く、M8号よりF6号の方が広いのです。
ところがF、P、Mは同価格という慣例から、M8がF8より安くなる事も無ければM8がF6より安く設定される事も無い様です。
キャンバスの規格がよくわからない数値な為、価格の決め方もいい加減に成らざるを得ない様です。
仮に”本当に面積で”価格を決めるとなると、各号、またS、F、P、M間の面積に相関性はないので全てに各々設定しなければなりません。
 F2号はF1号の倍ではなく、P4号でようやく倍程度の面積です。
F2号はF1号の倍ではなく、P4号でようやく倍程度の面積です。F100号はF1号のおよそ60倍の面積になります。
良く「1号はハガキ一枚分の大きさ」などと言いますが、ありゃ間違いです。
号は面積の単位にはなり得ません。
面積でなければ一体なにか。
現状で最も適切な答えは「長辺の長さ」でしょう。
10号の長辺は530mmです。これはS,F,P,Mどれも変わりません。
また10号の長辺とF6号の短辺318mmを組み合わせた場合、これは慣例的に「10号変形」と呼びます。
M6号の短辺242mmと組み合わせても「10号変形」。
ある程度までは価格もF10号と変わらない様ですが、短辺の長さがどれくらいになるまで価格は変わらないのか。
短辺の長さが1cmであったとしてもそれは「10号変形」になるのか。
それは知りません。
上記の様に「号」というのは、実はよくわからんものです。
号数のみで値段を決めようという行為はむちゃくちゃであり、破綻しています。
そもそも面積で作品の値段決めようって事自体バカげてると思いますが、
作家も画商も「号」は基準とはなり得ない事を理解した上で参考値程度にとどめ、価格なり画料の交渉には他の要素を十分加味し、柔軟性をもって臨むべきでしょう。
実はキャンバスサイズの規格には国際規格なるものが存在しており、そちらは号数毎の面積比などキッチリ比例しており、号数が異なると縦横比が異なるなんて事もありません。
しかし国際規格の木枠など画材店で見たことがありませんし、誰かが使ってる話も聞いたことがありません。
合理的で優れた規格でも、現行の「号」から外れる為、保守的な画商は価格設定などに困るでしょう。
また公募展でも現行の号を基準に規定のサイズが決められる為、国際規格などでは規定に収まらない可能性もあります。
既成額縁も国際サイズのものなどありはしませんから、難儀する事になります。
誰も使わなければ店にも置かないし、また取り寄せても割引がきかなかったりして、悪循環で普及しないんでしょう。
ここは現行「号」に異論を唱えるわたくし自らがそういうものを積極的に使っていくべきでしょうか。
写真の色はスケッチで補完。
形が変わるまでに描けないと思うモチーフは、まず写真を撮っておきます。
シロート撮影の写真の色はアテにならず、さらにプリントアウトした日にゃとんでもない色になってしまう事などザラなので、色については写真とは別に取っておく必要があります。
具体的には余分なキャンバスなどにザザッと油絵の具でスケッチをとっておく。
後に制作の際、形は写真をプリントアウトしたものを見ながらじっくり取って、色味はスケッチを参考に描くわけです。
実はこれ青木先生の手法で、最初面倒だなと思ってはいましたが、かなり有効であると思います。
写真のみで描いた後にあらかじめとっておいたスケッチと見比べてみるとまるで色が違っていたりします。
色が違う事自体は、意図的に色味を変えたりする事もあるし「ダメ」だとは思いません。しかし手元に残った素材が写真だけだと、ついつい何も考えずに写真の通りに描いてしまったりするんですな。
スケッチを取っといて、そちらの方が相当に鮮やかであったりすると、「やっぱ色取っといて良かったな…」などと思います。
しかしながらスケッチでは重ね塗りやグレーズの効果は出せず、カンペキな色の表現はできていません。
つまり製作時に色を再現するには写真やスケッチなどの素材以外の要素が必要になるのですが、結局やはり、そこは感性と技術で補完するよりありません。