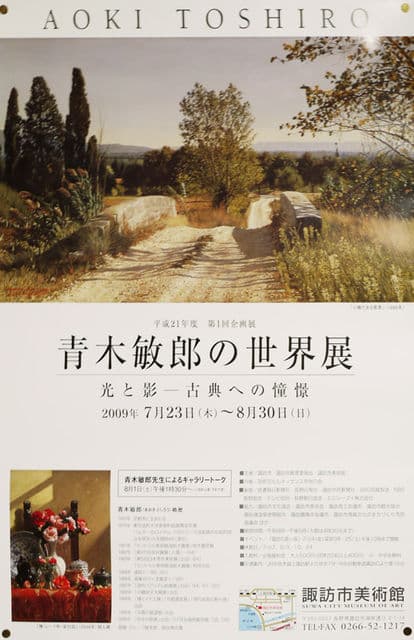DIYなお話。
結構長めのビスを使う機会があったのですが、これがもう硬くてカムアウトしまくりのナメまくりで往生します。
※「カムアウト」=溝からドライバーが浮き上がってガガガガッてなる事。
※ナメる=カムアウトによって溝が削られる事。
ナメちゃったビスはもう抜くのも大変だし、この世から消えて欲しい。
どうにかならんかと思い調べてみると、「スクエアビス」なる+でも-でもない、四角い穴の空いたビスがありまして、それがナメにくいとの事で、専用の「スクエアビット」と共に早速購入。
期待しながらいざ使ってみますと…全然ダメ。。
カムアウトしまくります。
どうもビットとビスのかみ合わせが悪いようで、ビットの先端ちょっとしかビスの穴に差し込めておりません。
こんなもんなの?
調べてみた。
一応規格ではNo1, No2, No3と3種類のサイズがあるが、
購入した新亀製作所のスクエアビットはそれぞれ約2.5mm、約3mm、約3.5mmとの表記。
Anex社では2.4mm(3/32インチ)、3.2mm(1/8インチ)、3.6mm(9/64インチ)。
VESSEL社は3/32インチ, 1/8インチ, 9/64 とインチ表記。
更に調べるとVESSEL社製ビットの注意書きに
“【注意】建築金物メーカーの株式会社栗山百造のビスについてはビットの収まりが悪いので、他メーカーのビットをご使用ください。”
とあった。
つまりメーカーによって微妙にサイズが異なるのか。
ビスとビットのかみ合わせが良いか悪いか、テメーで調べてから買えって事らしい。
なんじゃそりゃ。
ちなみに、何作ってんのかと言いますと、、、
いずれ作る予定の小屋裏収納へ通じる、収納階段の設置でした。
[続編]マキタ製 四角穴付コーススレッドと四角穴ビット